
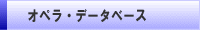
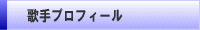
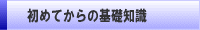
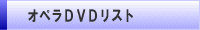
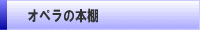
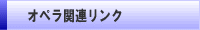
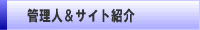
|
オペラを実際に見たことがある人は、少数派なのではないかと思います。でも、様々な「芸術」がある中で、総合芸術と呼ばれるオペラに興味がある人、気になっている人は、結構いるのではないでしょうか。しかも、クラシック音楽が好きであれば、オペラに関係する曲に自然と接することになりますし、好きな作曲家の書いたオペラを一度は見てみたいと思うはずです。
そんな人のためにガイド役になる本はないものかと探してみても、書店に置いてあるオペラの入門書のほとんどは「あらすじ集」ばかりでした。
何とか一度でも劇場にオペラを観にいってほしい、そして、オペラの「すごさ」を体験してほしい……。
オペラの素晴らしさを知ってほしいという気持ちから、劇場に足を運ぶためにチケットの入手法、予習の仕方、鑑賞のマナーまで踏み込んで解説したのが、前著『オペラにいこう!楽しむための基礎知識』でした。それまでの「あらすじ集」とは一線を画した初めての試みだったのではないかと思います。
幸い、前著『オペラにいこう!』を読んで、実際にオペラを観にいった人もいて、そのことを私にも報告してくれました。少しは本が役に立ったかなと思い、嬉しかったのですが、実はずっと気になっていることがありました。
初めてオペラを観にいって、十分楽しめたでしょうか?
次もまたオペラを鑑賞しようという気になれたでしょうか?
同じオペラでも、作曲された時代や場所によって全く別物のように印象が異なります。また、オペラには、「声」「歌」「音楽」「演出」などのあらゆる側面から「見かた聴きかた」が存在します。そこが総合芸術であるオペラの強みであり、複雑さでもあります。
本当はこうした諸々のことを知った上でオペラを鑑賞してみると、私たち受け手のアンテナが反応しやすくなって、オペラのことがよく見渡せるようになるはずなのです。
オペラについて、「声」「歌」「音楽」「演出」などのあらゆる側面から、順序立てて知ることができる本があればいいなと思って、本書『オペラ鑑賞講座 超入門』を書きました。本書を読めば、オペラを楽しむための「コツ」を掴むことができるのではないかと思います。
|
1. オペラを楽しむための「コツ」を解説
2. 知識ゼロから、まるで「講座」を受けているようにスムーズに理解できる
3. 文中で例として取り上げるオペラ作品は、名作オペラを厳選
4. 本文の内容にそって、随時、推薦CD、DVDを写真付きで紹介
5. 巻末には便利な「オペラ作品名索引」を掲載
|
まえがき
第1講 「オペラ」というジャンル
第2講 オペラと「クラシック音楽」
第3講 オペラの形式と種類
第4講 オペラの「歌」1 アリア
第5講 オペラの「歌」2 重唱と合唱
第6講 オペラの「音楽」
第7講 オペラの「演出」
第8講 実践1 『椿姫』の楽しみかた
〜なぜヒロインのヴィオレッタは「椿姫」と呼ばれるのか?〜
第9講 実践2 『蝶々夫人』の楽しみかた
〜日本を舞台にした悲劇的オペラ〜
第10講 実践3 『トスカ』の楽しみかた
〜激動のナポレオン時代に生きた主人公たち〜
第11講 実践4 『スペインの時』の楽しみかた
〜幸せはどこに転がっているかわからない〜
第12講 実践5 『フィガロの結婚』の楽しみかた
〜結婚後の二人の愛情のゆくえ〜
あとがき
引用・参考文献
オペラ作品名索引
|
|