
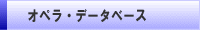
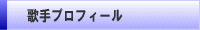
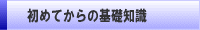
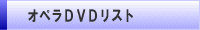
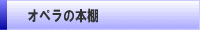
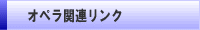
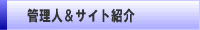
2023年新刊
名作オペラをやさしく解説
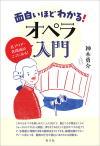
面白いほどわかる!
オペラ入門
名アリア名場面はここにある
神木勇介 著
青弓社 発行
定価1,800円+税
詳しくはこちら
|
オペラのことをいちから学ぶ
声、歌、音楽、演出について
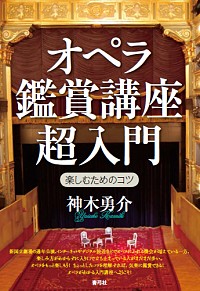
オペラ鑑賞講座 超入門
楽しむためのコツ
神木勇介 著
青弓社 発行
定価1,600円+税
詳しくはこちら
|
「オペラ情報館」が
本になりました

オペラにいこう!
楽しむための基礎知識
神木勇介 著
青弓社 発行
定価1,600円+税
詳しくはこちら
|
|
【作曲】
リヒャルト・シュトラウス 1940~41年に作曲
【初演】
1942年10月28日 ミュンヘン、国立歌劇場
【台本】
作曲者とクレメンス・クラウス(ドイツ語)
【演奏時間】
全1幕 約1時間20分
|
【時と場所】
1777年5月、パリ
【登場人物】
マドレーヌ(S): 伯爵令嬢
伯爵(Br): マドレーヌの兄
フラマン(T): 作曲家
オリヴィエ(Br): 詩人、劇作家
ラ・ローシュ(Bs): 劇場支配人、演出家
クレーロン(Ms): 女優
ムシュー・トープ(T): プロンプター
ほか
【全1幕】
時は1777年5月、舞台はパリ近郊の伯爵邸。若くして夫に先立たれたマドレーヌは、兄の伯爵とともにこの邸宅に住んでいます。彼女の誕生日に邸内の小劇場で新しい舞台作品を上演するため、劇場支配人ラ・ローシュ、作曲家フラマン、詩人オリヴィエが集まりました。フラマンは自分が作曲した弦楽六重奏に聴き入るマドレーヌを見て喜びますが、オリヴィエは自分の詩の方が上だと主張します。二人は彼女をめぐってライバル関係にありました。その二人に対してラ・ローシュは、舞台上の生身の人間こそ人の心を動かすものだと説きます。
弦楽六重奏を聴いていたマドレーヌのところに、兄の伯爵がやってきて、音楽よりも詩の「言葉」の方が優れていると言います。彼は女優のクローレンのことが好きで、彼女の朗読する詩に惚れ込んでいるのです。
マドレーヌは、フラマン作曲・オリヴィエ作詞のソネットを気に入ります。作曲家と作詞家がお互いに反発しあっても、このソネットの中では音楽と言葉は見事に結びついていると二人に言いました。
作曲家フラマンから求愛されたマドレーヌは困惑しましたが、明日の午前11時に邸内の図書室で会うことを約束します。
ラ・ローシュは新しい舞台作品に出演する歌手とダンサーを一同に紹介します。そして、マドレーヌの誕生日のための舞台として「パラス・アテネの誕生」と「カルタゴの没落」の2本立ての派手な大活劇とする計画を発表しますが、皆に反対されます。そこでマドレーヌが提案したのが、皆で協力して1つのオペラを作ることでした。妹からそのアイデアを聞いた伯爵は、今日の出来事をそのままオペラにすることを提案しました。
その夜、ただ一人、月の光が差し込む邸内のサロンに戻ったマドレーヌ。彼女は、詩人オリヴィエから伝言を受け取ります。伝言は、オペラの結末がどうなるのかを聞くために、明日の午前11時に図書室で待っているとのことでした。彼女は、フラマンと同じ約束をしたことを思い出し、二人が図書室で鉢合わせしてしまうと思いました。オペラの結末がどうなるのか、音楽を選ぶのか、言葉を選ぶのか、マドレーヌは鏡に映った自分に問いかけたのでした。
|
【1】 R.シュトラウスの最後のオペラ
『カプリッチョ』はR.シュトラウスが書いた最後のオペラです。シュトラウスはこのオペラを自身の劇作の最良の終わりと位置づけており、「人は遺書を一つしか書けない」と言いました。また、ヴェルディのオペラ『ファルスタッフ』を例に出し、老年のたのしみとして書きたいとしていました。そのためにシュトラウスと協力して台本を書いたのは指揮者のクレメンス・クラウスです。シュトラウスは、はじめ自分の手で台本を書こうとしたそうですが、クラウスと話しているうちにその方向性で一致し、彼に台本執筆を依頼しました。音楽に精通し、博識豊かなクラウスが書いた台本は、老作曲家の趣向――何ら感情陶酔のない、無駄のない機知――に合致するものでした。なお、カプリッチョとは音楽用語で「気まぐれな」を意味し、形式にとらわれない自由な楽曲を指します。
【2】 はじめに音楽、あとに言葉
シュトラウスがこのオペラを作曲した契機となったのは、アントニオ・サリエリ(1750-1825)が作曲したオペラ『はじめに音楽、あとに言葉』の存在を友人の作家シュティファン・ツヴァイクから聞いたことでした。このサリエリのオペラは、作曲家が先に用意した音楽に、詩人が後で台本をつけてオペラを完成させようとする無理なことを描いたオペラ・ブッファです。オペラにおける音楽と詩の主従関係については、昔から今日まで常に論点となってきました。シュトラウスはこの論点をそのままオペラとします。作曲家のフラマンと詩人のオリヴィエ――二人のうち、マドレーヌはどちらを選ぶのか、まさにオペラの結末がその答えとなりますが、その結末は描かれず、鑑賞する私たちに委ねられています。
【3】 カプリッチョの最終場面
このオペラの最大の聴きどころは、最終場面で誰もいなくなった舞台に一人残ったマドレーヌの歌唱「お兄さまはどちらに」"Wo ist mein
Bruder?"にあると言えるでしょう。その前に舞台には、プロンプターとしてムシュー・トープ(トーブ氏)が現れ、居眠りしていて自分のことが忘れられたと騒ぎ立てます。トーブ氏が去って静まった後、「月の光」と題された音楽が奏でられ、マドレーヌが登場するのです。そこでマドレーヌは、オペラの中で作られたオリヴィエ作詞、フラマン作曲のソネットを歌い始めます。フラマン(音楽)は美しい目と大きな魂を持ち、オリヴィエ(言葉)は強い理性と情熱を持つと言ってマドレーヌは鏡の前に立ち、自らの心を覗き込むのです。
|
【CD】
ベーム指揮
バイエルン放送交響楽団
ヤノヴィッツ(S) ディースカウ(Br) シュライアー(T) プライ(Br) リッダーブッシュ(Bs) トロヤノス(Ms)
(録音1971年、Deutsche Grammophon) |
|
 |
CDだけで楽しめるこのオペラには、この古典的な演奏をおすすめします。ベームのコクのある音楽が聴けますし、歌手陣には往年の名歌手がずらり。
【DVD】
シルマー指揮、カーセン演出
パリ・オペラ座
フレミング(S) ヘンシェル(Br) トロースト(T) フィンリー(Br) ハヴラタ(Bs) フォン・オッター(Ms)
(録画2004年、TDK Core) |
|
 |
設定をナチス支配下のパリとし、その上でマドレーヌ自身が、オペラの中で作られたオペラを見ているという演出が施されています。フレミングの歌唱とともに、配役も良い。
|
|