
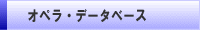
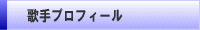
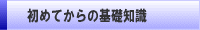
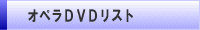
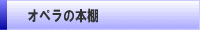
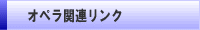
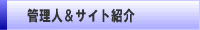
2023年新刊
名作オペラをやさしく解説
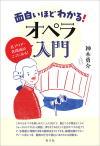
面白いほどわかる!
オペラ入門
名アリア名場面はここにある
神木勇介 著
青弓社 発行
定価1,800円+税
詳しくはこちら
|
オペラのことをいちから学ぶ
声、歌、音楽、演出について
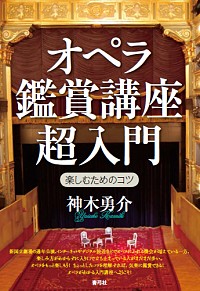
オペラ鑑賞講座 超入門
楽しむためのコツ
神木勇介 著
青弓社 発行
定価1,600円+税
詳しくはこちら
|
「オペラ情報館」が
本になりました

オペラにいこう!
楽しむための基礎知識
神木勇介 著
青弓社 発行
定価1,600円+税
詳しくはこちら
|
|
早めに到着して、プログラムを購入するのもおすすめです。プログラムは500円から1000円で買うことができます。外来オペラでは2500円から3000円することもあります。
もしオペラの予習をしないで来た場合は、最後の詰め込みのチャンスです。まず、あらすじに目を通しておきましょう。
次に大切なのは、指揮者や演出家がメッセージを寄せている場合です。
プログラムによっては、その日の公演の演出家が、公演の演出の「意図」を語っていることがあります。
現在のオペラ界は演出の時代でもあり、いろいろな趣向を凝らした舞台が上演されています。特にその演出家が独自の世界観を持ってオペラに取り組んだ場合、例えば、中世の物語を20世紀の物語にしたり、悲劇的なオペラを喜劇的に見せたり、そういう「読み替え」が行われることがあります。いきなりこのような舞台を見せられると、何が何だかわからないということにもなりかねません。客席が戸惑わないように、あらかじめプログラムに演出の意図を説明している場合があります。もちろん読み替えの演出の場合でなくても、演出家の強いこだわりをメッセージとして伝えることもあります。
こうしたメッセージは、私たちにとって、その意図が実際に舞台でどのように創造されたか、もしくは、されなかったかを見極める「きっかけ」にもなります。また、それとは逆に、私たち個人個人が、その演出家の意図に限られない多くのことを、勝手に受け取ってしまうことも多くあります。それはそれでいいことだと思います。そうした「私」と「演出家の意図」のギャップを感じることも、オペラという芸術を通して、自分を見つめ直す機会になったりするのではないでしょうか。
|
また、プログラムには、その公演に出演するキャストのプロフィールが掲載されています。これもよく見てみると、おもしろいのではないかと思います。一人のオペラ歌手が、これまでどのようにキャリアを積んできたのか。また、そのオペラ歌手が得意とするのは、どんな役か、どんな曲か。オペラにはイタリア系、ドイツ系、フランス系など、特徴ある様々な類似や差異があります。
こうしてオペラ歌手の歩んできた生き方にも目を通しておけば、その歌手の歌がまた違ったふうに聞こえてくるかもしれません。
|
最後に、オペラのプログラムには、音楽学者が様々な角度から、そのオペラの背景を解説しています。これらの論文を、実際に会場で読むことは時間的にも難しいかもしれません。その場合でも、あとで家に帰ってから、ゆっくりと読み直してみるのも楽しい一時となります。
オペラを理解するのに必要なこと、例えば、時代背景、民族、宗教、慣習などの知識を知っておくことは重要なことです。あらすじを読んでみて、少し引っかかった部分、わからないなと思った部分など、知らないことをこの機会に調べておくと、より深くオペラに接していくことができます。こうして得た知識というものは、オペラを通して実感として覚えていることが多いので、よく身に付くものです。芸術もたまには勉学の役に立ったりするのではないでしょうか。
|
|